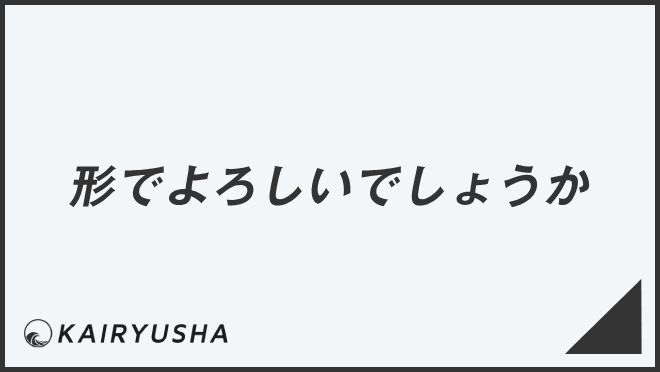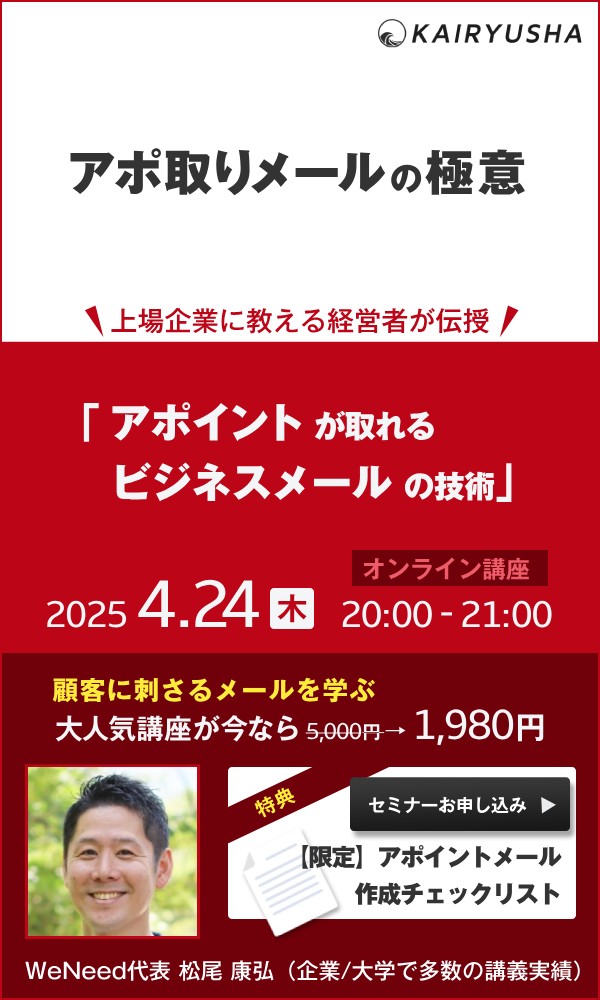この表現は、提案や報告の内容について、相手の承認や同意を求める場面で使われ、特にビジネスの場面では欠かせない表現の一つとなっています。相手への配慮と敬意を示しながら、確認を取る際の定番フレーズです。
- Qビジネスにおいて「形でよろしいでしょうか」の意味は?
- A
提案や内容について、相手の承諾を得るための丁寧な確認表現です。上司や取引先に対して使用され、相手の意見を尊重する姿勢を示します。
目次
「形でよろしいでしょうか」上司への正しい敬語の利用法
この表現は、複数の敬語要素で構成されています。言葉を分解して、敬語の種類別に見ていきましょう。| 構成要素 | 敬語の種類 | 説明 |
|---|---|---|
| 形で | 一般語 | 状態や内容を指す |
| よろしい | 丁寧語 | 「良い」の丁寧な表現 |
| でしょうか | 丁寧語 | 「ですか」をより丁寧にした表現 |

上司への報告時は、発言の前に「恐れ入りますが」を付けるとより丁寧になりますよ!
- 上司に対して使用する際は、声のトーンや表情にも気を配り、誠実な態度で話すことが大切です
- 複数の上司がいる場合は、全員に対して同じように丁寧な言葉遣いを心がけましょう
- 急ぎの用件であっても、この表現を省略せず、きちんと使用することが推奨されます
「形でよろしいでしょうか」の敬語を用いた言い換え
「このような形でお願いしてもよろしいでしょうか」
より丁寧な表現に言い換えた例です。「お願いして」を加えることで、より謙虚な印象を与えます。
より丁寧な表現に言い換えた例です。「お願いして」を加えることで、より謙虚な印象を与えます。
「この内容で進めさせていただいてよろしいでしょうか」
謙譲語を用いて、より丁寧さを強調した表現となっています。
謙譲語を用いて、より丁寧さを強調した表現となっています。
「このような方向性でご確認いただけますでしょうか」
相手の行為を尊重する表現を用いて、より丁寧に確認を求めています。
相手の行為を尊重する表現を用いて、より丁寧に確認を求めています。
「このような提案とさせていただきたく存じますが、いかがでしょうか」
非常にフォーマルな場面で使用できる、最上級の丁寧表現となります。
非常にフォーマルな場面で使用できる、最上級の丁寧表現となります。
「この案でご判断賜りたく存じますが」
「賜る」という最も丁寧な謙譲語を用いた表現です。
「賜る」という最も丁寧な謙譲語を用いた表現です。
「このような内容でご検討いただければと存じます」
控えめな依頼の形で表現することで、より柔らかい印象を与えます。
控えめな依頼の形で表現することで、より柔らかい印象を与えます。
「この方針でお進めさせていただきたく」
シンプルながら十分な敬意を示す表現として使用できます。
シンプルながら十分な敬意を示す表現として使用できます。
「こちらの内容でご承認いただけますと幸いです」
相手の承認を願う気持ちを込めた、丁寧な表現です。
相手の承認を願う気持ちを込めた、丁寧な表現です。
「このような形でご提案させていただきたく存じます」
提案時に使用できる、謙虚な姿勢を示す表現となっています。
提案時に使用できる、謙虚な姿勢を示す表現となっています。

相手の立場や状況に応じて、適切な言い換え表現を選びましょう!
・謙譲語や尊敬語を適切に組み合わせることで、より丁寧な表現になります。
・「させていただく」「存じる」などの謙譲表現を活用することで、より謙虚な印象を与えられます。
・相手の行為を表す際は「いただく」「賜る」などの敬語を使用し、敬意を示すことができます。
ビジネス例文一覧
ビジネスシーンでは、様々な場面で「形でよろしいでしょうか」を活用できます。特に報告や提案、確認の際に重宝する表現です。状況や相手によって適切な使い方があり、以下の例文を参考に、場面に応じた使用を心がけましょう。TPOを考慮しながら、相手に失礼のない丁寧な表現として活用してください。
修正した企画書、この形でよろしいでしょうか。
来週水曜日15時からの会議開催という形でよろしいでしょうか。
予算案は以上のような形でよろしいでしょうか。
改訂版の報告書、この形でよろしいでしょうか。
今回はこういった形でよろしいでしょうか。
プロジェクトの進め方として、以上のような形でよろしいでしょうか。
作成した見積書につきまして、この形でよろしいでしょうか。
ご提案は以上の形でよろしいでしょうか。
契約書の最終案として、この形でよろしいでしょうか。
では、そのような形でよろしいでしょうか。

提案や確認の際は、具体的な内容を明確に示してから使用しましょう!
また、例文では「以上の」「以上のような」「そのような」など、文脈に応じた接続表現を使用することで、より自然な会話の流れを作り出しています。ビジネスの現場で実際によく使用される表現となっています。
「形でよろしいでしょうか」ビジネスでの意味合い
ビジネスにおいて、この表現は単なる確認以上の意味を持ちます。相手の意見を尊重し、柔軟な対応の余地を残しながら、提案や確認を行う際の重要な表現です。特に、上司や取引先との対話において、適切な距離感と敬意を示すことができ、ビジネスマナーの基本として定着しています。

相手の立場や状況を考慮して、適切なタイミングで使用することが大切ですよ!
- 提案や報告の際に相手の意見を尊重する姿勢を示し、円滑なコミュニケーションを図るための重要な表現です。慎重に扱うべき案件や重要な決定事項の際に特に効果的です。
- ビジネスにおける「確認」の作法として定着しており、特に文書やメールでのやり取りにおいて、適切な距離感を保ちながら意思確認を行うための標準的な表現として認識されています。
- 相手に選択の余地を与え、柔軟な対応を可能にする表現として機能します。直接的な要求や指示とは異なり、相手の意見や判断を重視する姿勢を示すことができます。
ビジネスメール作成例
掲題:会議資料の修正案について
株式会社ビジネスソリューション
田中様
いつもお世話になっております。
先日の打ち合わせでご指摘いただきました会議資料の修正が完了いたしましたので、ご報告させていただきます。
第3章の販売戦略の部分を中心に、ご意見を反映した内容となっております。添付資料にてご確認いただけますと幸いです。この形でよろしいでしょうか。
来週の定例会議での使用を予定しておりますので、お手数ではございますが、今週金曜日までにご確認いただけますと助かります。
ご不明点等ございましたら、お申し付けください。
よろしくお願いいたします。
グローバルマーケット株式会社
営業企画部
鈴木健一
株式会社ビジネスソリューション
田中様
いつもお世話になっております。
先日の打ち合わせでご指摘いただきました会議資料の修正が完了いたしましたので、ご報告させていただきます。
第3章の販売戦略の部分を中心に、ご意見を反映した内容となっております。添付資料にてご確認いただけますと幸いです。この形でよろしいでしょうか。
来週の定例会議での使用を予定しておりますので、お手数ではございますが、今週金曜日までにご確認いただけますと助かります。
ご不明点等ございましたら、お申し付けください。
よろしくお願いいたします。
グローバルマーケット株式会社
営業企画部
鈴木健一

メールは簡潔に要点をまとめ、確認したい内容を明確に示すことがポイントですよ!
「形でよろしいでしょうか」は、文章の真ん中あたりで使用し、その後に具体的な依頼事項を記載するのが効果的です。
「形でよろしいでしょうか」を使うビジネスシチュエーション
この表現は、ビジネスシーンにおいて相手の承認や同意を得る必要がある場面で多用されます。特に、提案や報告の際に、相手の意見を尊重する姿勢を示すために重要な役割を果たします。状況に応じて適切に使用することで、円滑なコミュニケーションを図ることができます。

相手の立場や案件の重要度を考慮して、使用のタイミングを見極めましょう!
- 企画書や提案書の内容確認を依頼する際に、修正案や最終版の承認を求める場面で使用します
- 会議やミーティングの日程調整において、候補日を提示する際の確認表現として活用できます
- 業務の進め方や方針について、上司や関係者の同意を得る必要がある場合に使用します
- プロジェクトの中間報告や最終報告の際、内容や形式の確認を求める場面で効果的です
- 取引先との契約内容や条件について、最終確認を行う際の丁寧な表現として使用できます
- 社内文書やプレゼンテーション資料の体裁について、承認を得る場面で活用します
「形でよろしいでしょうか」間違った使用法
この表現を適切に使用するには、いくつかの注意点があります。誤った使用は、かえって不自然な印象を与えたり、コミュニケーションの障害となったりする可能性があります。
確認すべき内容を具体的に示さずに使うのは避けましょう!
- 「この形だけでよろしいでしょうか?」
→「だけ」という限定的な表現を加えることで、消極的な印象を与えてしまいます - 「この形でよろしいですか?」
→「でしょうか」を「ですか」に変えると、丁寧さが不足します - 「こういう形でよろしいでしょうか」
→「こういう」という口語的な表現は、ビジネス文書では避けるべきです - 「データ集計はこれぐらいの形でよろしいでしょうか」
→曖昧な表現を避け、「この形で」とします - 「この形でよろしいでしょうかね」
→語尾に「ね」をつけることで、確認の意図が曖昧になってしまいます
まとめ
「形でよろしいでしょうか」は、ビジネスシーンにおける確認の基本表現として、広く活用されています。相手への敬意を示しながら、円滑なコミュニケーションを図る上で重要な役割を果たします。特に文書やメールでのやり取りでは、この表現を適切に用いることで、専門性と礼儀正しさを両立させることができます。ただし、使用する際は場面や状況を十分に考慮し、最適なタイミングで活用することが大切です。
また、この表現は単なる確認以上の意味を持ち、相手の意見を尊重する姿勢や、柔軟な対応の可能性を示唆する効果もあります。ビジネスパーソンとして、このような表現を使いこなすことで、より円滑なコミュニケーションが実現できるでしょう。