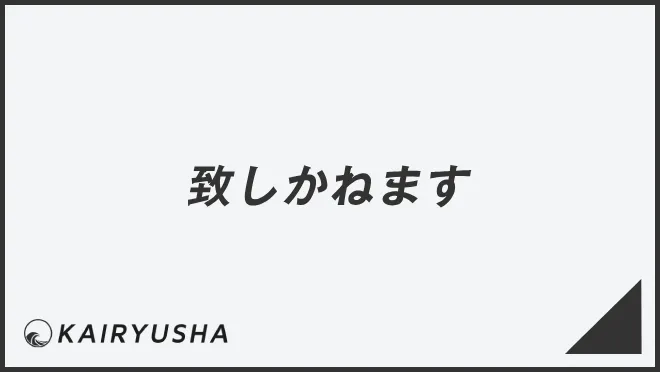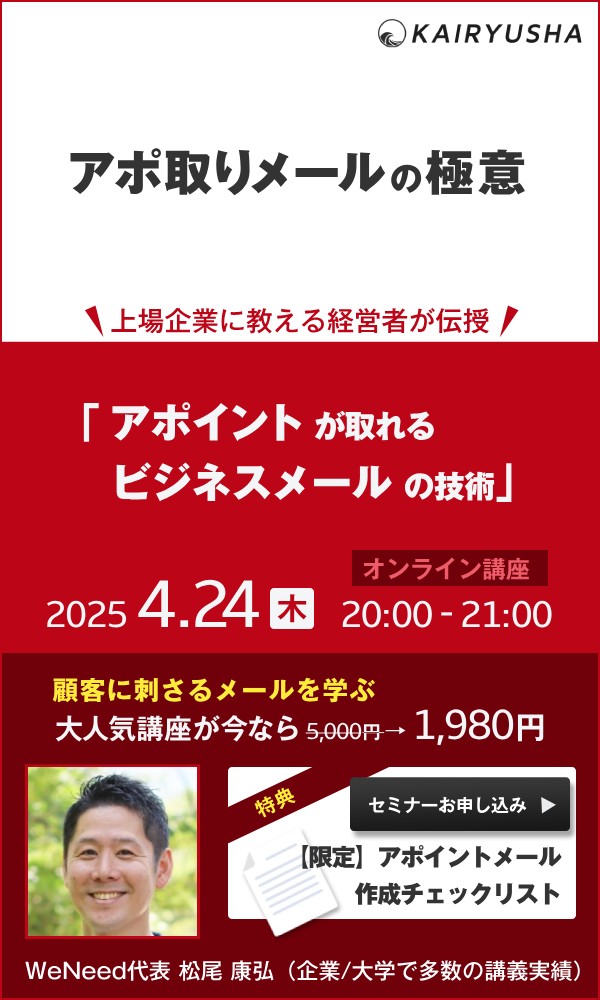「致しかねます」は、ビジネスシーンでよく使用される丁寧な断り表現です。相手の要望や依頼に対して、やむを得ず実行できない状況を表現する際に使用される言葉です。
この言葉は、相手への配慮を示しながらも、明確な断りの意思を伝えることができる重要なビジネス用語でしょう。断りの表現でありながら、礼儀正しく丁寧な印象を与えることができる表現ですね。
-
Qビジネスにおいて「致しかねます」の意味は?
-
A
要望や依頼を受けることができない場合に使用する丁寧な断りの表現です。相手への敬意を示しながら、できない理由を説明する際に使われます。
「致しかねます」ビジネスにおける意味
ビジネスの場面において、「致しかねます」は相手の要望や依頼に対して、実行が困難であることを丁寧に伝える表現として使用されます。単なる「できません」よりも、より丁寧で礼儀正しい印象を与えることができる言葉ですね。
この表現は、相手への配慮を示しながらも、明確な意思を伝えることができる重要なビジネス用語でしょう。特に取引先や上司との会話において、断りを伝える際に適切な表現として用いられます。

断る理由を明確に説明し、代替案を提示できる場合は併せて提案しましょう!
| 使用場面 | 効果 | 注意点 |
|---|---|---|
| 取引先との会話 | 丁寧な印象を与える | 理由説明が必要 |
| 上司への返答 | 礼儀正しさを示す | 代替案の提示が望ましい |
- 相手の要望や依頼に対して、実行が困難である場合に使用します。その際、なぜできないのかという理由を明確に説明することが重要です。
- 単なる断りではなく、相手への配慮や敬意を示す表現として使用されます。特に、取引先や上司との会話において、適切な距離感を保ちながら意思を伝えることができます。
- この表現を使用する際は、代替案を提示することで、より建設的なコミュニケーションを図ることができます。できない理由を説明した後に、別の解決策を提案することで、相手との良好な関係を維持することができます。
ビジネスの例文
「致しかねます」を使用する際は、必ず理由を明確に説明し、相手に誠意を持って対応することが重要です。また、可能な代替案を提示することで、より建設的なコミュニケーションを図ることができます。
状況に応じて、「申し訳ございませんが」や「誠に恐れ入りますが」などの前置きを加えることで、より丁寧な印象を与えることができるでしょう。
言い換えと類語
より直接的な断りの表現で、明確な意思を示す必要がある場合に使用します。
「致しかねます」よりもやや柔らかい印象を与える表現ですね。
依頼や要望を受けられない場合に使用する丁寧な表現です。
「致しかねます」と同様の意味を持つ、やや格式高い表現になります。
相手の理解を求める際に使用する、柔らかい断りの表現でしょう。
直接的な断りを避けたい場合に使用する婉曲的な表現ですね。
要望に応えられない場合に使用する、明確な断りの表現になります。
業務上の理由で実行できない場合に使用する表現です。
言い換え表現を使用する際は、状況や相手との関係性を考慮して適切な表現を選択することが重要です。また、断りの理由を明確に説明し、可能であれば代替案を提示することで、より円滑なコミュニケーションを図ることができます。
「致しかねます」をビジネスで使う効果的な場面
ビジネスシーンにおいて、「致しかねます」は相手への配慮を示しながら断りを伝える際に効果的な表現です。特に取引先や上司との会話において、適切な距離感を保ちながら意思を伝えることができます。

断る際は必ず代替案を用意して、建設的な提案をしましょう!
- 取引先からの無理な要求への対応:納期や価格など、企業として受け入れられない条件が提示された場合に使用します。
- 社内規定に反する依頼への返答:コンプライアンスや社内ルールに抵触する要望に対して使用します。
- 技術的に実現が困難な案件:技術的な制約により実現が難しい要望に対して使用します。
- 予算的な制約がある場合:予算面での制約により、要望に応えられない場合に使用します。
- 人員体制上の理由:現状の人員体制では対応が困難な場合に使用します。
- 品質保証の観点:品質維持が困難な要望に対して使用します。
ビジネスメール用法
ビジネスメールで「致しかねます」を使用する際は、断りの理由を明確に説明し、誠意を持って対応することが重要です。また、可能な代替案を提示することで、より建設的なコミュニケーションを図ることができます。
株式会社山田製作所
佐藤様
いつもお世話になっております。
先日ご依頼いただきました納期短縮につきまして、社内で検討いたしました。
誠に申し訳ございませんが、品質保証の観点から、ご要望の納期での対応は致しかねます。
現状では、最短で来月15日の納品となりますが、いかがでしょうか。
なお、特急対応をご希望の場合は、別途費用が発生いたしますが、10日での納品も可能です。
ご検討いただけますと幸いです。
ご不明な点がございましたら、お気軽にご連絡ください。
メールを作成する際のポイントは以下の通りです。
1. 断りの理由を明確に説明する
2. 代替案を提示する
3. 丁寧な言葉遣いを心がける
4. 相手の立場に立って配慮する
5. 前向きな姿勢を示す
「致しかねます」顧客に使う敬語
「致しかねます」は、複数の敬語要素で構成される丁寧な表現です。
- 「致す」:「する」の謙譲語であり、話者が自分の行動を謙虚に表現します。
- 「かねる」:「できない」の意味を丁寧に表現する補助動詞です。
- 「ます」:丁寧語として文末に付加され、全体として敬意を表します。
顧客に使用する際は、以下の点に注意が必要です。
1. 必ず理由を説明する
2. 代替案を提示する
3. 適切な前置きを使用する
4. 誠意を持って対応する
「致しかねます」間違った使用法
- 理由なしでの使用:「申し訳ございませんが、それは致しかねます」
→理由を説明せずに断るのは、相手に不信感を与える可能性があります。 - 断りのみの使用:「その件については致しかねますので、ご了承ください」
→代替案を提示せずに断るだけでは、建設的なコミュニケーションとは言えません。 - 説明不足:「技術的な理由により致しかねます」
→具体的な説明がないため、相手の理解を得ることが難しくなります。 - 不適切な前置き:「すみませんが致しかねます」
→ビジネス場面では、より丁寧な前置きを使用すべきです。 - 唐突な使用:「それは致しかねます。以上です」
→唐突な断りは、相手との関係性を損なう可能性があります。
まとめ
「致しかねます」は、ビジネスシーンにおいて重要な断りの表現として活用されています。相手への配慮を示しながら、明確な意思を伝えることができる表現ですね。
この言葉を効果的に使用するためには、適切な理由説明と代替案の提示が不可欠です。また、状況に応じて適切な前置きを使用することで、より円滑なコミュニケーションを図ることができるでしょう。
ビジネスにおいては、断りの表現も重要なスキルの一つです。「致しかねます」を適切に使用することで、相手との良好な関係を維持しながら、clear な意思伝達が可能になりますね。
最後に、この表現は単なる断りではなく、より良いビジネス関係を築くためのコミュニケーションツールとして活用することが重要です。状況を適切に判断し、建設的な対話を心がけましょう。