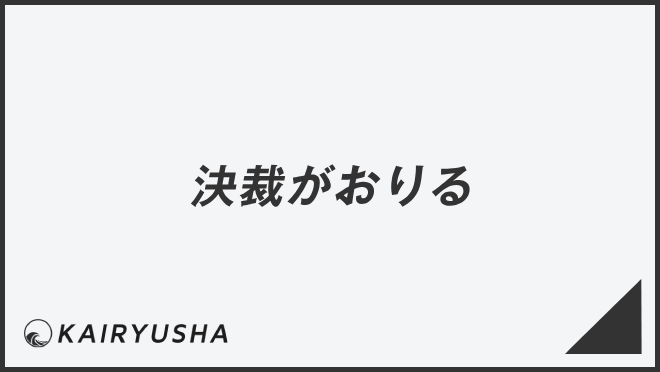「決裁がおりる」は、ビジネスにおいて重要な承認プロセスを表す表現です。上司や決定権者から、提案や企画に対して正式な許可が得られることを意味します。
通常、書類や申請の審査を経て、承認者から正式な許可が下りることを指します。この表現は、特にビジネスシーンで頻繁に使用される重要なフレーズとなっています。
-
Qビジネスにおいて「決裁がおりる」の意味は?
-
A
会社内での提案や計画について、責任者から正式な承認を得ることです。プロジェクトや予算の執行が可能になる重要な判断となります。
「決裁がおりる」ビジネスにおける意味

決裁申請の前に、数字的な根拠と期待される効果を明確にまとめておきましょう!
- 提案や企画に対して、決定権を持つ上位者から正式な承認を得ることを指します。通常、部長級以上の決裁権限を持つ役職者からの承認を意味することが多いでしょう。
- 承認プロセスには、書類審査や会議での説明、質疑応答などの手続きが含まれます。決裁者の判断に必要な情報や資料を適切に準備することが重要です。
- 決裁がおりることで、予算の使用や人員の配置、プロジェクトの開始など、具体的なアクションを取ることが可能になります。組織的な活動の正式な開始点となる重要な意味を持ちます。
ビジネスで使える例文
ビジネスシーンでは、決裁に関する進捗状況や結果を伝える場面が多くあります。以下の例文は、様々な状況で活用できる表現をまとめたものです。フォーマルな表現から、やや柔らかい表現まで、場面に応じて使い分けることができます。
これらの例文は、決裁の状況を適切に伝えるための基本的な表現となっています。状況に応じて、より丁寧な表現や、より簡潔な表現を選択することが重要です。
特に、決裁の見通しを伝える場合は、確実性の度合いに応じて表現を使い分けることがポイントとなります。また、決裁が確定した場合は、具体的な日時や経緯を含めることで、より正確な情報伝達が可能になります。
ビジネスでのメール作成例
山田商事株式会社
佐藤様
いつもお世話になっております。
先日ご提案させていただきました新規プロジェクトについて、ご報告申し上げます。
本日、弊社にて検討を重ねておりました件について、正式に決裁がおりる運びとなりました。
つきましては、来週より具体的な進行スケジュールについて、ご相談させていただければと存じます。
ご多忙のところ恐縮ではございますが、ご都合の良い日時をご教示いただけますと幸いです。
何卒よろしくお願い申し上げます。
株式会社テクノフューチャー
営業部 鈴木一郎
メール作成のポイントは、以下の3つです。
1. 決裁の結果を明確に伝えることが重要です。あいまいな表現は避け、具体的な進捗状況や今後の展開について説明しましょう。
2. 相手先への敬意を示しながら、スムーズな連携を図るための提案を含めることがポイントです。決裁後の具体的なアクションプランを示すことで、プロジェクトの円滑な進行が期待できます。
3. 文章全体の構成を整理し、簡潔かつ分かりやすい表現を心がけることが大切です。特に、決裁に関する報告は、ビジネスの重要な転換点となるため、正確な情報伝達が求められます。
「決裁がおりる」をビジネス使う効果的な場面
ビジネスシーンでは、様々な場面で決裁の状況を伝える必要があります。適切なタイミングと表現方法を選択することで、円滑なコミュニケーションが可能になります。

決裁後の具体的なアクションプランも併せて準備しておくと、スムーズな展開が期待できますよ!
- 新規プロジェクトの立ち上げ時:大規模なプロジェクトを開始する際、予算や人員配置など、重要な経営判断が必要な場面で使用します。関係者への報告や、今後の進め方について説明する際に適切な表現となります。
- 取引先との交渉時:商談や契約の進行状況を説明する場面で、社内での承認状況を伝えるために使用します。特に、重要な案件の進捗報告時には、決裁の状況を明確に伝えることが重要です。
- 予算申請の報告時:部門やチームの活動に必要な予算について、承認状況を報告する場面で使用します。特に、年度予算や追加予算の申請結果を伝える際に適切な表現となります。
- 人事関連の通知時:異動や昇進、採用などの人事関連の決定事項を伝える場面で使用します。正式な承認を得たことを示す際の適切な表現として活用できます。
- 設備投資の報告時:新規設備の導入や、既存設備の更新について、承認状況を報告する場面で使用します。投資規模が大きい案件では、特に重要な表現となります。
- 社内制度の変更時:新しい制度やルールの導入について、正式な承認を得たことを伝える場面で使用します。全社的な影響がある案件では、特に慎重な表現が求められます。
「決裁がおりる」目上の人に使う敬語
「決裁がおりる」は、ビジネスシーンで頻繁に使用される表現ですが、目上の人に対しては適切な敬語表現が必要です。

敬語表現は相手の立場や状況に応じて使い分けることが大切ですよ!
- 基本形:「決裁がおりる」
– 「決裁」:名詞(特別な敬語形なし)
– 「おりる」:動詞の謙譲語
– 「が」:助詞(変化なし) - 敬語表現:
– 「ご決裁をいただく」(謙譲語)
– 「ご決裁くださる」(尊敬語)
– 「ご決裁を賜る」(最も丁寧な謙譲語)
役職が上の方に対しては、「ご決裁を賜る」など、より丁寧な表現を選択することが望ましいでしょう。また、決裁者の立場や状況に応じて、適切な敬語レベルを選択することが重要です。
決裁に関する報告や相談の際は、説明の内容だけでなく、話し方や態度も含めて、相手への敬意を示すことを心がけましょう。
言い換え&類語大全

場面や相手に応じて適切な表現を選ぶことで、より効果的なコミュニケーションが実現できますよ!
正式な許可を取得する際の一般的な表現として広く使用されています。
比較的カジュアルな場面でも使いやすい、柔らかい印象の表現でしょう。
特に公的機関や重要案件に関する承認を示す際に適した表現となります。
関係者間での同意を強調したい場面で効果的な表現です。
社内での正式な承認プロセスを表現する際によく使用される言葉ですね。
比較的軽微な案件や日常的な承認事項について使用される表現となっています。
幅広い場面で使える、汎用性の高い表現として知られています。
特に権利関係や契約に関する承認を示す際に使用される表現でしょう。
相手の同意を丁寧に表現する際に適した言い回しとなります。
会議や委員会での承認を示す際によく使用される表現です。
提案や企画が選ばれて承認されることを示す際の表現として適しています。
言い換えをする際のポイントは、状況や文脈に応じて適切な表現を選択することです。フォーマルな場面では「承認を得る」「認可される」などの表現が適していますね。
一方、社内での日常的なコミュニケーションでは「許可が下りる」「了承される」といった、やや柔らかい表現も使えるでしょう。特に重要な案件については、「稟議が通る」「可決される」など、正式な手続きを強調する表現を選ぶことをお勧めします。
「決裁がおりる」間違った使用法
決裁に関する表現は、ビジネスシーンで重要な役割を果たすため、正しい使用が求められます。以下に、よくある間違いと、その理由を解説します。

決裁に関する表現は、正確さと適切な敬意が重要ですよ!
- ×「決裁を得る」(上司に対して)
○「ご決裁をいただく」
解説:上司に対して「得る」は敬意が不足します。適切な敬語表現を使用する必要があります。 - ×「決裁がおります」(決裁者が自分で言う場合)
○「決裁します」
解説:決裁権者が自身の決定について話す場合、「おりる」という表現は不適切です。 - ×「決裁がおりてくる」
○「決裁がおりる」
解説:「おりてくる」は口語的すぎる表現です。ビジネス文書では「おりる」を使用します。 - ×「決裁が通る」
○「決裁がおりる」
解説:「通る」は非公式な表現であり、正式な文書や重要な報告では適切ではありません。 - ×「決裁がもらえました」
○「決裁がおりました」
解説:「もらう」という表現は、決裁のような公式な承認プロセスを表現する際には適切ではありません。決裁は組織的な判断であり、個人的な授受を示す「もらう」は使用を避けるべきです。 - ×「決裁が出ました」
○「決裁がおりました」
解説:「出る」という表現は非公式過ぎます。正式な承認プロセスを示す際は、「おりる」を使用するのが適切です。
「決裁がおりる」まとめ
ビジネスシーンにおいて「決裁がおりる」は、組織的な意思決定の重要な要素を表す表現です。適切な使用は、円滑なコミュニケーションと業務進行の鍵となります。
特に注目すべきは、状況や相手に応じた表現の使い分けです。フォーマルな場面では敬語表現を、社内の日常的なやりとりではより柔らかい表現を選択することで、効果的なコミュニケーションが可能になります。
また、決裁に関する報告や連絡は、ビジネスの重要な転換点となることが多いため、正確さと適切なタイミングが求められます。特に、進捗状況や今後の展開について、具体的な情報を含めることで、関係者との認識共有が促進されるでしょう。
最後に、決裁は組織としての意思決定を示すものであり、その表現方法は企業文化や業界慣習によっても異なります。場面に応じた適切な表現を選択し、ビジネスコミュニケーションの質を高めていくことが重要です。