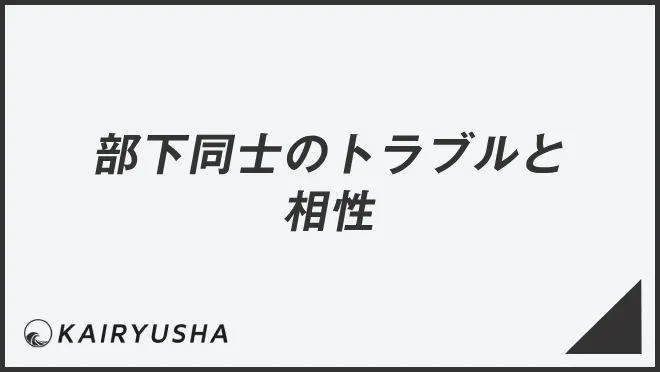職場では様々な個性や価値観を持った人々が集まり、共に働いています。そのため、部下同士の相性が合わずにトラブルが発生することは珍しくありません。管理職として、こうした状況にどう対応すべきか悩むことも多いでしょう。
本記事では、部下同士のトラブルや相性問題に対して、管理職がどのように対応すべきかについて解説します。効果的なコミュニケーション方法や役割分担の明確化など、実践的なアプローチを紹介していきます。
部下同士のトラブルが組織に与える影響
部下同士のトラブルは、単なる個人間の問題にとどまらず、組織全体にさまざまな悪影響を及ぼします。特に放置すると、業務効率の低下やチーム全体の士気の低下につながる恐れがあります。
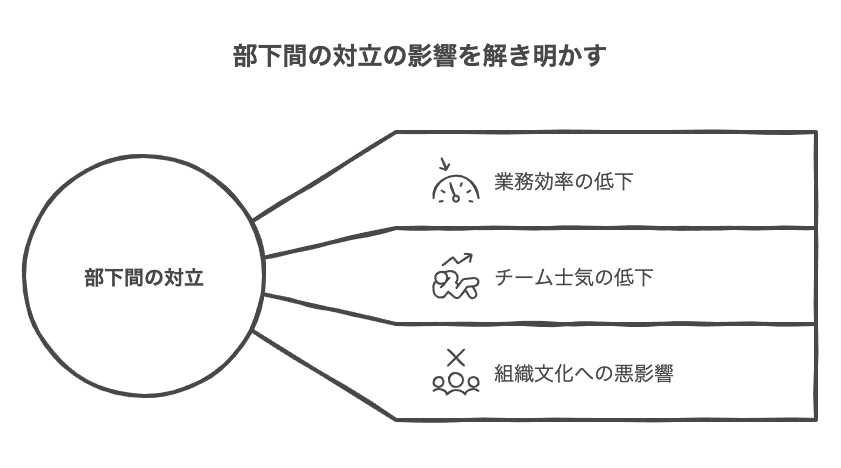
業務効率と生産性への影響
部下同士が対立していると、必要な情報共有がスムーズに行われなくなります。お互いに協力すべき場面でも、コミュニケーションが不足し、結果として業務の遅延や質の低下を招きます。
例えば、プロジェクトの進行中に部下同士が口をきかない状態になると、本来なら5分で済む確認作業が、メールのやり取りや第三者を介することで何時間もかかってしまうことがあります。これは明らかな時間の無駄であり、組織全体の生産性を著しく下げる要因となります。

部下同士のトラブルを「大人なんだから自分たちで解決して」と放置するのは危険です。小さな火種が組織全体の大火災になる前に、適切な介入が必要です。
職場の雰囲気と他メンバーへの波及
部下同士のトラブルは当事者だけの問題ではありません。周囲のメンバーも気を遣うようになり、職場全体の雰囲気が悪化します。特に深刻なケースでは、チーム内で派閥が形成され、さらに大きな分断を生む可能性もあります。
職場の雰囲気が悪くなると、創造性や積極性が失われ、メンバーの心理的安全性が脅かされます。その結果、新しいアイデアの提案や率直な意見交換が減少し、組織の成長や革新が妨げられることになるのです。
部下同士のトラブルは、放置すればするほど解決が難しくなり、組織全体のパフォーマンスを低下させる深刻な問題です。
相性問題の根本原因を理解する
部下同士の相性問題には、様々な原因が考えられます。効果的な解決策を見出すためには、まずその根本原因を理解することが重要です。
価値観やコミュニケーションスタイルの違い
多くの場合、部下同士のトラブルは価値観やコミュニケーションスタイルの違いから生じます。例えば、直接的な表現を好む人と遠回しな表現を好む人では、同じメッセージでも受け取り方が大きく異なります。
また、仕事に対する姿勢や優先順位の違いも対立の原因となります。効率重視のタイプと丁寧さ重視のタイプが同じチームにいると、互いの仕事の進め方に不満を感じることがあるでしょう。
- 仕事の進め方の違い(計画的 vs 臨機応変)
- コミュニケーションスタイルの違い(直接的 vs 間接的)
- 責任感の違い(細部まで確認 vs 大枠を重視)
- 時間感覚の違い(余裕を持つ vs ギリギリまで粘る)
役割と責任の不明確さ
役割と責任が明確に定義されていないと、「誰がやるべきか」という点で対立が生じやすくなります。特に業務の境界線が曖昧な場合、お互いに「相手がやるべき」と思い込み、結果として必要な仕事が抜け落ちたり、逆に重複して行われたりすることがあります。
例えば、プロジェクトの進捗管理について明確な担当者が決まっていないと、「なぜ報告してくれなかったのか」「それはあなたの役割だと思っていた」といった行き違いが発生します。こうした状況が積み重なると、次第に個人間の不信感へと発展していくのです。

相性の悪さを個人の問題と片付けるのは簡単ですが、多くの場合、組織の仕組みやルールの不備が根本原因になっています。自分自身のマネジメントスタイルも振り返ってみましょう。
部下同士の相性問題は、単なる性格の不一致ではなく、多くの場合、役割の不明確さやコミュニケーションの行き違いが根本原因となっています。
効果的なトラブル解決のアプローチ
部下同士のトラブルに対して、管理職としてどのようにアプローチすべきでしょうか。ここでは具体的な解決方法を紹介します。
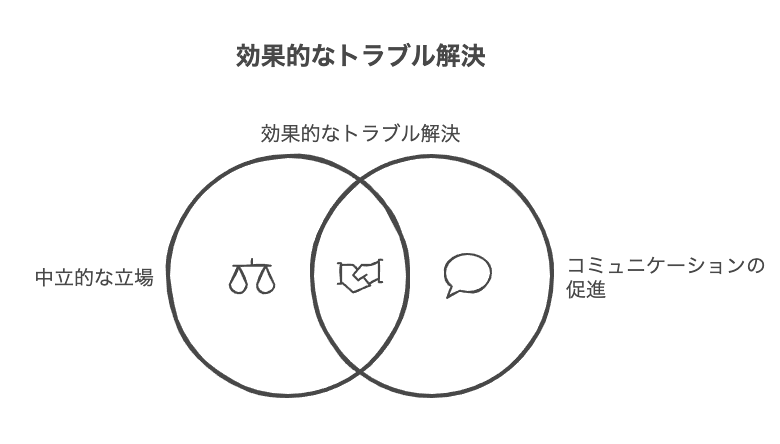
コミュニケーションの場を設定する
トラブルを解決するためには、まず当事者同士が直接対話する場を設けることが重要です。ただし、感情的になりやすい状況では、管理職が適切にファシリテートする必要があります。
対話の場を設ける際のポイントは、「事実」に焦点を当てることです。「あなたはいつも〜する」といった一般化や、「あなたは〜だから」という人格批判ではなく、具体的な出来事とそれによって生じた影響について話し合うよう促しましょう。
例えば、「先週の会議で意見を遮られたとき、自分の提案が評価されていないと感じた」というように、具体的な状況と感情を結びつけて表現するよう指導します。
- まずは個別に話を聞き、それぞれの認識を把握する
- 共通の目標を確認し、チームとしての方向性を再確認する
- 当事者同士の対話の場では、感情ではなく事実に焦点を当てる
- 互いの良い点や貢献を認め合う機会も作る
役割と責任の明確化
多くのトラブルは、「誰が何をいつまでに行うか」が明確になっていないことから発生します。管理職として、チーム内の役割分担を明確にし、それぞれの責任範囲を文書化することで、不必要な摩擦を減らすことができます。
特に重要なのは、「みんなで」「協力して」といった曖昧な表現を避け、具体的に担当者と期限を決めることです。これにより、「自分だけが頑張っている」「あの人は責任を取らない」といった不満の発生を防ぐことができます。

「ルールがあるから人間関係が窮屈になる」と考える人もいますが、実は逆です。明確なルールがあるからこそ、余計な気遣いや忖度なく、自由に仕事ができるのです。
トラブル解決の鍵は、感情的な対立を事実ベースの建設的な対話に変換し、「誰が何をいつまでに」という明確な役割分担を確立することにあります。
相性問題を予防するマネジメント術
部下同士のトラブルは、発生してから対応するよりも、予防することが理想的です。ここでは、相性問題を未然に防ぐためのマネジメント術を紹介します。
チームビルディング活動の実施
定期的なチームビルディング活動は、メンバー間の相互理解を深め、信頼関係を構築するのに役立ちます。ただし、形式的なイベントではなく、メンバーが本音で交流できる場を作ることが重要です。
例えば、業務に関連するワークショップや、各自の強みを活かしたプロジェクトなど、単なる親睦会ではなく、実際の仕事に関連した活動を通じて理解を深めることが効果的です。これにより、普段の業務では見えない相手の長所や考え方を知る機会となります。
- 各メンバーの強みを可視化するワークショップ
- 異なる部署や役割を体験する短期ジョブローテーション
- チーム全体で取り組む小規模なプロジェクト
- 定期的な振り返りミーティングの実施
マネジメントの柔軟性を高める
すべての部下に対して同じアプローチで接するのではなく、それぞれの特性や強みに合わせたマネジメントスタイルを採用することも重要です。これは「お気に入り」を作るということではなく、各メンバーの能力を最大限に引き出すための戦略的なアプローチです。
例えば、細かい指示がないと不安になるタイプの部下には具体的なガイドラインを提供し、自主性を重視するタイプには大枠だけを示して裁量を与えるなど、柔軟に対応することで、それぞれが最高のパフォーマンスを発揮できる環境を整えることができます。

相性問題の解決に「時間が経てば自然に解決する」というアプローチは危険です。小さな火種のうちに対処することで、大きな炎上を防ぐことができます。
また、どうしても相性が合わないメンバー同士の場合は、業務上の接点を最小限にする工夫も必要です。席の配置を変更したり、プロジェクトの担当を調整したりすることで、不必要な摩擦を減らすことができます。
相性問題の予防には、チームビルディング活動を通じた相互理解の促進と、各メンバーの特性に合わせた柔軟なマネジメントアプローチが効果的です。
よくある質問
回答 対立が発生した初期段階では、まず部下たち自身で解決する機会を与えることが理想的です。しかし、完全に放置するのではなく、状況を注意深く観察しましょう。対立が長引いたり、業務に支障をきたしたり、感情的になってきた場合は、早めに介入することが重要です。介入する際は、まず個別に話を聞いて各自の認識を把握し、その後、共通の場で建設的な対話ができるよう支援します。「大人なんだから自分たちで解決して」という姿勢は、問題を悪化させる可能性があるため避けましょう。

小さな火種は早期に対処することが重要です。「時間が解決してくれる」と思って放置すると、いつの間にか組織全体に影響を及ぼす大きな問題に発展していることがよくあります。
回答 チーム編成の変更は最終手段として検討すべきでしょう。まずは相性の悪さの根本原因を理解し、コミュニケーションの改善や役割の明確化などで解決を試みることが重要です。多くの場合、相性の悪さは単なる性格の不一致ではなく、コミュニケーションスタイルの違いや役割の曖昧さから生じています。
それでも改善が見られない場合は、プロジェクトの担当調整や席の配置変更など、直接的な接点を減らす工夫を検討しましょう。チーム編成の変更は、組織全体に影響を与える可能性があるため、慎重に判断する必要があります。
回答 公平性を保つためには、以下のアプローチが効果的です:
双方から個別に話を聞き、それぞれの視点を理解する
感情ではなく事実に焦点を当てた対話を促す
特定の人の味方をしているように見える言動を避ける
共通の目標や組織の方向性を再確認し、個人的な対立から視点をシフトさせる
必要に応じて、人事部門など第三者の介入を検討する
重要なのは、単に「公平」であるだけでなく、関係者全員が公平に扱われていると感じられるプロセスを構築することです。透明性を保ち、すべての意見に耳を傾ける姿勢を示すことで、信頼関係を築くことができます。

「公平」と「平等」は異なります。すべての人に同じ対応をすることが公平とは限りません。それぞれの状況や特性に合わせた対応をすることが、真の公平性につながるのです。
回答 頻繁にトラブルが発生するチームには、通常、より深い組織的な問題が潜んでいます。根本的な解決には以下のアプローチを検討してください:
役割と責任の明確化:誰が何をいつまでに行うかを文書化し、曖昧さをなくす
コミュニケーションルールの確立:情報共有の方法や会議の進め方など、基本的なルールを設ける
チームビルディング活動の実施:メンバー間の相互理解を深める機会を定期的に設ける
フィードバック文化の醸成:日常的に建設的なフィードバックを交換できる環境を作る
マネジメントスタイルの見直し:あなた自身のマネジメント方法が対立を生んでいないか振り返る
特に重要なのは、「みんなで」「協力して」といった曖昧な表現を避け、具体的に担当者と期限を決めることです。明確なルールと期待値を設定することで、不必要な摩擦を減らすことができます。
回答 チーム全体のモチベーション低下に対処するには、まず部下同士のトラブルを迅速に解決することが最優先です。その上で、以下の対策を講じましょう:
チーム全体での対話の場を設ける:トラブルがチームに与えた影響について率直に話し合う機会を作る
共通の目標を再確認する:個人間の対立よりも大きな組織の目標や意義を思い出させる
小さな成功体験を作る:達成可能な短期目標を設定し、成功体験を共有する
貢献を認める文化を強化する:メンバー同士が互いの貢献を認め合う機会を意図的に作る
必要に応じて組織変更を検討する:深刻な場合は、チーム構成や業務分担の見直しも視野に入れる
モチベーション回復には時間がかかることを理解し、継続的なサポートと観察が必要です。一度失われた信頼を取り戻すには、一貫した行動と誠実なコミュニケーションが不可欠です。

チームのモチベーション回復には「見える化」が効果的です。進捗状況や成果を視覚的に共有することで、個人間の対立を超えた「チームとしての成長」を実感できるようになります。